日本の公的年金受給者と確定申告
公的年金と税金
日本では、公的年金を受給している方も税金を支払う必要があります。公的年金は「雑所得」として扱われ、所得税と住民税の課税対象となります。年金収入から源泉徴収される所得税の税率は、20.42%(復興特別所得税を含む)です。
毎年1月頃に、日本年金機構から「公的年金等の源泉徴収票」(年金通知)が送られてきます。この源泉徴収票には、年間の年金受給額、源泉徴収された所得税額、社会保険料などが記載されています。これらの情報をもとに、自分がいくら税金を支払ったのか、払いすぎたのか、それとも足りないのかを確認することができます。もし払いすぎていれば、確定申告をすることで還付を受けることができます。また、年金受給額が一定額以下の場合や、低所得・無職の場合には、その年に限り年金に対する税金の全額または一部の免除を申請することができます。
確定申告が必要なケース
原則として、年金受給者は確定申告をする必要があります。しかし、「確定申告不要制度」という制度があり、一定の条件を満たせば確定申告は不要となります。この制度は、高齢者の確定申告の手続きに伴う負担を軽減するために設けられています。確定申告が必要となる主なケースは以下の通りです。
- 公的年金等の収入金額が400万円を超える場合
- 公的年金等以外の所得金額が20万円を超える場合 この場合の「公的年金等以外の所得金額」には、生命保険契約に基づいた個人年金や生命保険の満期返戻金なども含まれます。
- 外国の年金制度など、日本で源泉徴収がされない年金を受給している場合
確定申告が不要なケース
確定申告不要制度の対象となるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下である。
- その公的年金等のすべてが源泉徴収の対象となる。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である。
確定申告不要制度の対象者であっても、住民税の申告が必要になる場合があります。例えば、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されていない控除(生命保険料控除・損害保険料控除・医療費控除など)の適用を受ける場合などです。詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお問い合わせください。
確定申告不要制度の対象者でも確定申告をした方が良いケース
確定申告不要制度の対象者であっても、以下のような場合には確定申告をすることで税金が還付される可能性があります。
- マイホームを住宅ローンなどで取得した場合
- 医療費控除などの各種控除を受けたい場合
- 災害や盗難にあった場合
- 「扶養親族等申告書」を提出していない場合
「扶養親族等申告書」は、年金から源泉徴収される所得税について、配偶者控除などの各種控除を受けるために必要な申告書です。この申告書を提出していない場合でも、確定申告をすることで納めすぎた所得税が戻ってくる場合があります。
確定申告の注意点
確定申告を行う際には、以下の点に注意しましょう。
- 提出期限は3月17日です。
- 確定申告書には、「公的年金等の源泉徴収票」などの必要書類を添付する必要があります。確定申告書を作成する際には、源泉徴収票が必要となりますので、大切に保管しておきましょう。
- 確定申告は、税務署に直接行くか、郵送、またはe-Taxで行うことができます。
- ご自身の「公的年金等の源泉徴収票」をよく確認しましょう。源泉徴収票には、確定申告が必要かどうかを判断するために必要な情報が記載されています。
退職金と税金
退職金は、従業員が退職後に生活の基盤を確保するための手段として、社会的に重要な役割を担っています。そのため、退職所得は税制上優遇されています。しかし、近年では、企業が従業員の給与を減額し、その減額分を退職金として支払うことで、退職所得の優遇税制を利用し、従業員の所得税を減らすというケースが増えてきました。こうした問題に対処するため、2021年の税制改正では、勤続年数5年未満の従業員に対して、退職所得の課税所得を計算する際の50%の標準控除が認められなくなりました。この改正は、2022年以降に支給される退職金から適用されます。
まとめ
公的年金を受給している方は、確定申告が必要かどうか、ご自身の状況をよく確認しましょう。確定申告不要制度の対象者であっても、確定申告をすることで税金が還付される可能性があります。 わからないことがあれば、税務署や市区町村の窓口に相談することをおすすめします。
参考資料
WordPress形式
この記事はWordPress形式で記述されています。見出し、段落、箇条書きなどを適切に使用し、読みやすさに配慮しています。
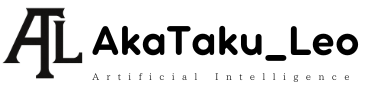



コメント