物流クライシスとは
現在、日本社会はトラックドライバー不足に起因する「物流クライシス」に直面しています。EC・通販で購入した商品が翌日に届く、スーパーに新鮮な食品が毎日並ぶといった私たちの当たり前の日常が維持できなくなる危機に瀕しています。
物流DXを妨げる障壁
1. デジタル化を理解しない経営陣
物流業界でDX(デジタルトランスフォーメーション)を進めようとする際、主に50〜60代の経営陣が障壁となるケースが多く見られます:
- 「システム導入をするならば費用対効果を出せ!」と言い、実質的にDXを妨害
- システム導入の費用対効果を説明しても「事務員たちの給料はもともと発生しているから比較対象にならない」と突っぱねる
- 「システムなんか導入しなくとも、今までどおり事務員さんたちにがんばってもらえばいいじゃないか?」という考え方
ある中堅運送会社の勉強会では、運送会社の役員が「紙と鉛筆が大好きで、ITに触れようとしてこなかった旧世代の運送会社の社長や役員たちが、偉そうに『システム導入をするならば費用対効果を出せ!』と言って、私たちの物流DXを妨害してくる」と嘆いています。
2. デジタル化を嫌うドライバー
50〜60代のトラックドライバーもデジタル化を妨げる要因となっています:
- 手書きの運転日報をデジタルタコグラフ(デジタコ)からの出力に変更しようとしても、「面倒くさい」と反発
- デジタコ操作は「これから荷物を積みます」「荷物を積み終わりました」といったステータスボタンを押すだけの簡単な作業だが拒否する
ある中小運送会社の社長は「手書き運転日報に固執する老害ドライバーのせいで、若い事務員が残業をしなければならない。50歳を超えたおじさんのわがままによって、10代の女の子が残業をさせられるって理不尽です」と嘆いています。
物流業界の非効率性
物流業界は長年、消費者や荷主のわがままを「我々がなんとかしなければ!」と受け止め、十分な対価も得られないまま人海戦術で対応してきました。その一例として:
- 輸入段ボールに傷がついていると「見栄えが悪い」という理由で、同じ仕様の新しい段ボールに詰め替える作業が行われている
- こうした非効率な作業が物流現場に強いられている
物流DXの必要性
人手不足の深刻化により人海戦術に限界が生じている今、限られた人手でも生産性向上を実現するためにDXが必要です:
- 物流DXはシステム導入だけでなく、ロボットや自動化機器、自動運転、ドローン物流なども含む
- 「ロボットなんて使えない」「自動運転なんていつ実現するんだよ?」と否定・冷笑する50〜60代が妨げとなっている
著者の主張
物流DXは「できるか、できないか」の議論ではなく、「成し遂げて物流クライシスを回避しないと日本社会の維持継続に重大な危機が生じる」社会的に意義ある取り組みです。物流は「産業の血液」と称されますが、現状のままでは早晩その役目を果たせなくなり、日本の産業界は動脈硬化を起こします。
著者は「人生の半ばを既に折り返しているおじさん・おばさんたちが、若者たちの未来を作ろうとする取り組みの足を引っ張るのはなんとも情けない」と指摘し、老害の排除を訴えています。
まとめ
物流クライシスが深刻化した時に重大なダメージを被るのは若者たちです。小さなこだわりや現状維持バイアス、ITやデジタルが苦手という理由で物流DXを排除しようとする人々には、物流が社会に果たす役割と物流DXの重要性を再考することが求められています。
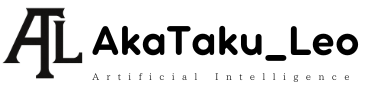



コメント