ドーパミンは一般的に「幸せホルモン」として知られていますが、専門家によると、この認識には大きな誤解があります。日本経済新聞に掲載された記事をもとに、ドーパミンの真の役割と一般的な誤解について解説します。
ドーパミンの本当の役割
ドーパミンは複雑な神経伝達物質で、以下のような多様な機能を持っています:
- 学習、運動、記憶、注意力の調整
- 気分やモチベーションの制御
- 脳内のニューロン間のコミュニケーション促進
重要なのは、ドーパミンは「気分を良くする」効果を直接持つわけではないという点です。カナダ・モントリオール大学の薬理学・生理学准教授のアン・ノエル・サマハ氏は、「ドーパミンは快楽物質ではなく、快楽を求める物質」と説明しています。
脳内部位による異なる影響
ドーパミンが脳内のどの部位で増えるかによって、人に与える影響が変わります:
| 脳の領域 | ドーパミン増加の影響 |
|---|---|
| ある特定領域 | 集中力が高まる |
| 別の領域 | 衝動的になる |
特定の領域でドーパミンが不足すると、集中力や運動機能に悪影響が出ることもあり、これが注意欠如・多動症(ADHD)、パーキンソン病、依存症などの原因となります。
歴史的な誤解の起源
なぜドーパミンが「快楽物質」と誤解されるようになったのでしょうか?
- 1986年に学術誌「Journal of Neurophysiology」で発表された研究で、食べ物などの報酬を受けた時に脳がドーパミンを放出することが示された
- この研究から「ドーパミン=快楽」という考え方が広く受け入れられた
- しかし1990年代から2000年代初頭にかけて、これを否定する証拠が出てきた
- ドーパミン系を遮断した動物でも報酬を受け取ると喜ぶことが確認された
- ただし「もっと手に入れようとするやる気」は完全に失われた
「ドーパミンラッシュ」の誤解
インターネットやSNSでは「ドーパミンラッシュ(大量放出)」や「ドーパミン断ち」というキーワードが広まっていますが、専門家はこの考え方に問題点を指摘しています:
- 楽しい活動に携わるとドーパミンは確かに増えるが、この感情の高まりを「ドーパミンラッシュ」と呼ぶのは単純化しすぎ
- 快楽に関わるのはドーパミンだけでなく、セロトニン、オキシトシン、エンドルフィンなど他の神経伝達物質も重要な役割を果たす
- ドーパミンの上昇は本質的には良くも悪くもない
- 重要なのは、極端にならないこと(多すぎれば躁状態に、少なすぎればうつ状態になる危険性)
「ドーパミン禁断症状」は実際には存在しない
一般的に言われる「ドーパミン禁断症状」についても誤解があります:
- 習慣を変える時に一時的に不安やストレスを感じることはあるが、これはドーパミンの大幅減少によるものではない
- 医学的な「ドーパミン受容体作動薬の離脱症候群」は存在するが、これはパーキンソン病などの治療薬を使用していた一部の人だけに起こる症状
- 旅行から帰ってきた後の陰うつな気分などは、ストレスのない生活の高揚感に慣れただけであり、深刻なドーパミン不足ではない
「ドーパミン断ち」の本来の意味と誤解
2019年に「ドーパミン断ち」という言葉を生み出した心理学者は、刺激の多い社会に対する「解毒」という意味でこの言葉を使いました。しかし、この概念は誤解されています:
- スマートフォンのタップだけで得られる「事前の作業がほとんどいらない強力な報酬」が常に与えられる生活
- その結果、本来好きなことでも満足できなくなるが、「基本的なドーパミンレベルを通常の健全な状態に戻そう」として好きなものを求め続ける
- 本来の意図は衝動的な問題行動を制限することであり、ドーパミンを完全に断つことではない
スタンフォード大学医学部の精神医学・依存症医学教授で『ドーパミン中毒』の著者であるアンナ・レンブケ氏も指摘するように、「ドーパミンを完全に断つことなどできない」のです。サマハ氏は「禁酒日を設けるのとは違って、禁ドーパミン日を作ることはできません」と説明しています。
結論
サマハ氏の言葉が重要です:「ドーパミンが本来の働きをするということを信じ、後はそっとしておきましょう」。有害な習慣を避けるのは良いことですが、自分を幸せにするものまで避ける必要はありません。
ドーパミンについての理解を深めることで、私たちの脳の仕組みや行動の動機をより正確に捉えることができるでしょう。
出典:日本経済新聞 電子版 2025年3月24日 5:00
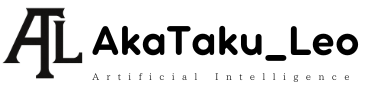



コメント