前提
- 文章をAIで書くこと自体はOK
- AIっぽさ、人間っぽさを理解して、AI以上間味のある文章を書いていけるようになることが大事
- 特に自分のすでに手間隙をかけることも必要
AIっぽくならないための5つのコツ
1. 具体的な経験や体験談を盛り込むよう指示する
文章の一般性能から文章を脱却させるため、実際の体験的になりがち。体験や経験を伝えて物語を語ることで具体的な文章になる。
指示例: 「私が○○したときのように、具体的なエピソードを交えて文章を作ってください。たとえば、実際に旅行で悔しい経験や教えたほど、そこで出会った人の印象など、生活に密着した事例を盛り込むようにして。」
AIっぽい例: 「イタリアンレストランで食事をするとき、ピザとパスタを注文することをおすすめします。」
AIっぽくない例: 「昨年の夏、イタリアのフィレンツェを訪れたとき、路地裏の小さなジェラート屋で食べたヘーゼルナッツが忘れられない。あの暑さのなか、地元の人にとって身近な食べ物で冷えた一皿が心地よい風味と新たに興味に目覚めさせた。」
2. 言葉遣いにバリエーションを持たせるよう指示する
AIの文章は一定のパターンで構成されることが多く、表現に変化が少ない。表現の違いを意識させることで自然な文章になる。
指示例: 「同じ意味でも使える言い回しを工夫し、語彙力を豊かに入れて、リズム感のある自然な文章を作成してください」
AIっぽい例: 「この商品には多くのメリットがある。まず便利であることが挙げられる。また、多機能であることも魅力だ。そして、コストパフォーマンスの高いこともわかる。」
AIっぽくない例: 「使ってみて本当いいのは、その手軽さ。ポンと開けてサクッと使えるだけでなく、豊富な機能が詰め込まれているからだ。しかも価格のわりにコスパがいいものだから、長く愛用できるだろうと感じた。」
3. 感想や感情を明示する言葉を入れるよう指示する
AI文章は論理構成に偏しがちで感情的な訴えが足りない。人の感情表現を「悲しかった」「はっとした」「もどかしい」などの感情表現を取り入れることで、読み手に生命感のある文章と受け取られる。
指示例: 「悲しいや嬉しい、もどかしさなど、具体的な感情表現を加え、読み手により自分の感かみ伝わるようにしてください」
AIっぽい例: 「この音楽は多くの人に認められており、国際的にも高く評価されている。技術的完成度も高い。」
AIっぽくない例: 「この曲を初めて聴いたとき、胸に迫る感動に涙が止まらなかった。それほどに聴き手の心の琴線に触れる力強さがこの曲にはあり、いくらここで語っても伝わらない気がした。」
4. ストーリー性や文脈を作るよう指示する
AI文章は事実や情報だけが並んだ文章になりがち。話の流れを持たせるようにストーリー性を持たせたり、複数の背景を盛り込むよう指示する。
指示例: 「時系列や因果関係がわかるような流れのある文章を作ってください。始まり、展開、結論という構成で、読者が飽きることなく興味を持って読めるようにしてください。」
AIっぽい例: 「最近、電車の中で年配の人が若者に席を譲ってもらうことが増えた。スマートフォンの普及と高齢化社会、ライフスタイルの変化といった様々な社会データでも分析が可能である。」
AIっぽくない例: 「先日、電車内のなか席譲りをめぐって自分が恥ずかしい思いをした。ベビーカーを抱えたお母さんだったが、運良く席が空いたときにはすでに別の乗客が座っていなかった。お礼も、統計データでも分析が可能はするかもしれないが。」
5. 逆説や「ムダ」や「脱線」を取り入れるよう指示する
論理整合性だけではなく脱線、逆説を意図的にいれるようにする。逆説やずれや脱線は、意外性や個性の表れであり大切な要素。
指示例: 「全部筋が通りすぎないように、時には少しずれた小さなエピソードやニュービトピックを交えてください。これにより、文章に味と遊びが生まれます。」
AIっぽい例: 「このサービスを使えば人の業務負担は確実に減少し、効率化のアップが望めている。」
AIっぽくない例: 「うちの職場は時間にゆずれにくく、硬すぎの雰囲気もちや何かするのが面倒くさい雰囲気をしているう。こういうやわらかい表現も良いかもしれない雰囲気的なものも大切だが、やっぱり機能これが大事だろう。」
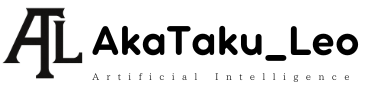
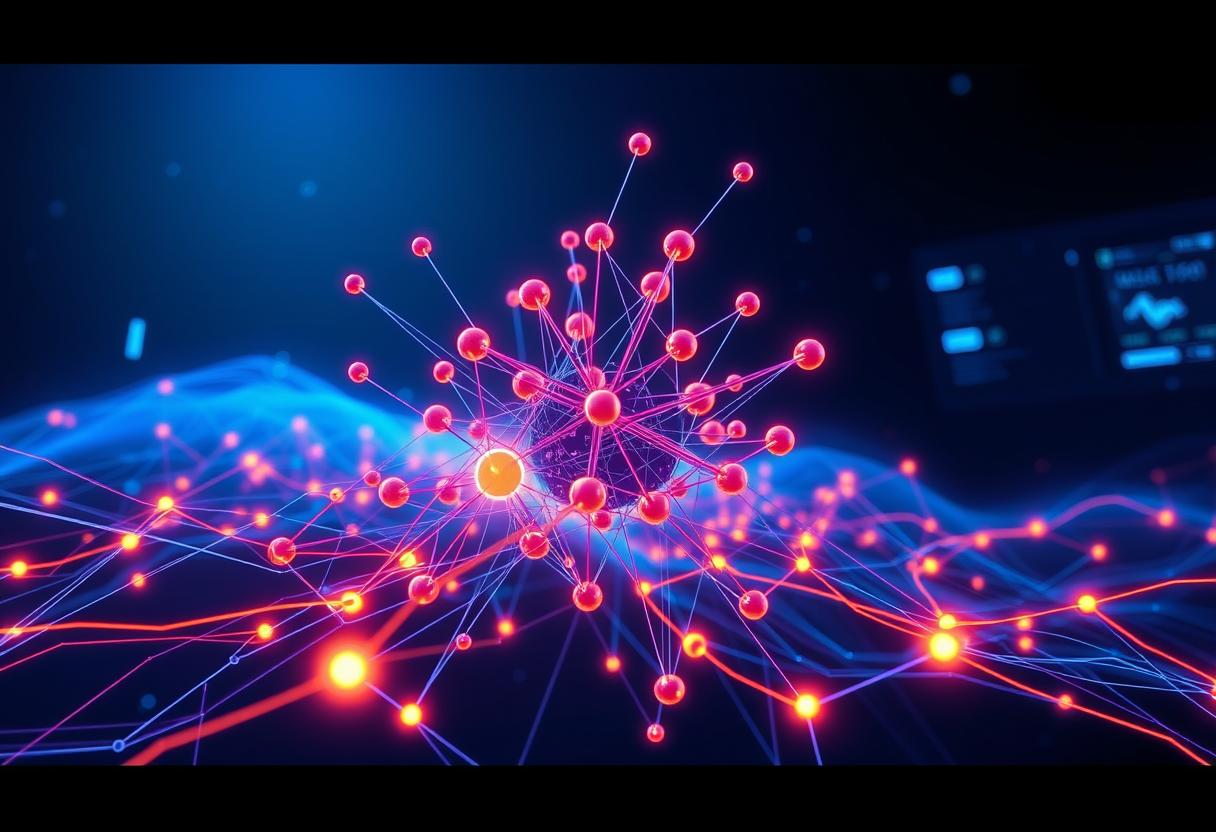


コメント