1月の世界平均気温が観測史上最高!一方、日米は最強寒波と大雪に見舞われる
2025年2月26日付でSMBC日興証券の金融財政アナリスト 末澤豪謙氏が発表した内容によると、1月の世界平均地表気温は観測史上最も高い記録(13.23℃)を更新しました。一方で、日本や米国では過去最大級の寒波と大雪が襲来し、極端な気象現象が同時に発生するという一見矛盾する状況が見られます。
世界平均気温の記録更新とその背景
WMO(世界気象機関)やEU傘下のコペルニクス気候変動サービス、米海洋大気局(NOAA)のデータによると、2025年1月の世界平均地表気温は13.23℃に達しました。これは、1991年~2020年の平均より0.79℃高く、産業革命以前(1850~1900年)の平均よりは1.75℃高い数値です。さらに、過去19か月のうち18か月で、産業革命以前の基準値よりも1.5℃以上高い状態が続いており、地球温暖化の進行が顕著であることを示しています。
日米に襲来した最強寒波と記録的な大雪
一方、北米東部・南部では、偏西風の蛇行や極渦の伸長が影響し、今回の寒波で約6000万人以上が零度以下の低温にさらされました。米国全体では、1月に約1億500万人が極端な低温を経験し、過去の記録を更新する勢いです。日本では、冬型の気圧配置と強い寒気の影響で、特に日本海側において過去数十年で稀な大雪が観測され、一部地域では積雪が5メートルを超えるなど、記録的な寒波と大雪が同時に発生しました。
極渦と偏西風の蛇行がもたらす異常気象
通常、ラニーニャ現象が発生すると、海面水温が平年より低下し一時的な寒冷化が起こるとされています。しかし、今年1月はエルニーニョ現象も確認されていない状況下で、最高気温記録が更新されました。これは、極渦の伸長現象と、北極圏と中緯度地域との温度差の縮小が、偏西風の速度低下と蛇行を引き起こし、結果として極寒の空気が南下する現象を招いたためです。 また、米国では、湖水効果が大雪の要因として働いており、寒冷な空気が相対的に暖かい湖上を通過する際に発達する雪雲が、記録的な降雪をもたらしました。これらの現象は、温暖化による気候システムの不安定化を背景にしており、局地的な寒冷現象と同時に、世界平均気温の上昇という矛盾する状況を生み出しています。
地球温暖化と今後の展望
地球温暖化は、単に平均気温が上昇するだけでなく、極端な気象現象の頻発という形でも現れています。北極圏の急速な温暖化や海氷の減少、グリーンランドおよび南極の氷床の融解は、今後の海面上昇や地域ごとの気候変動に大きな影響を与える可能性があります。NOAAや英国気象庁の予測によれば、2025年は世界全体で記録的な高温を示す年となる一方で、局地的には依然として冷夏や異常気象のリスクが残るとされています。 これに伴い、農林水産業への影響、インフレの進行、さらには移民・難民問題や地政学的リスクの拡大が懸念され、各国での適応策や温暖化対策が一層求められる時代となっています。
まとめ
1月の記録的な高温は、地球温暖化の明確な証左でありながら、一方で日米を中心とした地域での最強寒波や大雪は、温暖化による気候システムの不安定化がもたらす副産物と言えます。極渦の伸長、偏西風の蛇行、湖水効果など、複数の要因が絡み合って発生するこれらの現象は、今後も私たちの生活や社会に大きな影響を及ぼすことが予想されます。 今後の気候変動に対する備えや、温暖化対策の強化が急務となる中、世界と地域それぞれの状況に応じた対策が求められています。読者の皆様も、今一度気候変動の現状とその影響について考えてみてはいかがでしょうか。
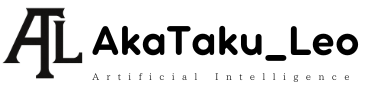



コメント