東京では現在、自動運転タクシーの実証実験が活発に行われています。本記事では、主要なプレイヤーの動向や技術、そして将来展望についてまとめました。
エグゼクティブサマリー
東京は自動運転タクシーサービスの開発と実証における重要な舞台となっています。米Alphabet傘下のWaymo社が、タクシーアプリ「GO」と日本交通との提携を通じて、2025年から東京都心部での車両テストを開始する予定です。これはWaymoにとって初の米国外での事業展開となります。
同時に、国内企業の株式会社ティアフォーも、オープンソースソフトウェア「Autoware」を基盤に、レベル4自動運転技術の開発と実証を積極的に推進しています。2027年までの都内全域でのサービス展開という野心的な目標を掲げています。
これらの動きは、MONET TechnologiesとMay Mobilityによる実証実験や、本田技研工業とGM Cruiseによるレベル4サービス計画、日産自動車の計画など、他の企業やコンソーシアムによる取り組みと連動して進んでいます。
主要プレイヤーの動向
Waymoの日本市場への参入
Waymoは、タクシーアプリ「GO」を提供するGO株式会社、および大手タクシー事業者の日本交通株式会社と提携し、2025年から東京都心部での技術テストを開始します。初期段階では、Waymoの車両は日本交通の訓練された乗務員による手動運転で、データ収集が主な目的となります。
テスト地域は東京都心の7つの区(港区、新宿区、渋谷区、千代田区、中央区、品川区、江東区)で行われ、車両にはジャガーの電動SUV「I-PACE」が使用されます。
Waymoの自動運転システム「Waymo Driver」は、車両に搭載された多数のセンサー(高解像度カメラ、LiDAR、ミリ波レーダーなど)からの情報を統合・処理し、周囲の状況を360度認識・理解することで自動運転を実現します。
ティアフォーの取り組み
国内企業のティアフォーは、オープンソース自動運転ソフトウェア「Autoware」の開発を主導し、「自動運転の民主化」をビジョンに掲げています。日本交通と協力してタクシー営業車両に高性能センサーを搭載し、大量の走行データを収集しています。
ティアフォーは、お台場や西新宿などで「プレサービス実証」と称する実証実験を実施してきました。これらの実験ではレベル2での運用が行われ、運転席には運転士が搭乗し、必要に応じて手動運転に切り替える形式でした。
商業化計画としては、2024年11月から東京都内の限定区画(お台場など)でロボットタクシー(レベル4水準)のサービス実証を開始し、2025年までに都内3箇所、2027年には都内全域でのサービス提供を目指しています。
その他の主要プレイヤー
- MONET Technologies / May Mobility: ソフトバンクとトヨタの合弁会社であるMONET Technologiesは、米国のMay Mobilityと協力し、東京臨海副都心での自動運転技術を用いた移動サービスの実証実験を行いました。レベル2での運用で、将来的には2029年度までにレベル4運行を目指しています。
- 本田技研工業 / GM Cruise: 本田技研工業はGM傘下のCruiseと提携し、運転席のない完全自動運転(レベル4)専用車両「クルーズ・オリジン」を使用した移動サービスを計画しています。2026年初頭のサービス開始を目標としています。
- 日産自動車: 2025年後半から一般利用者向けのサービス実証実験を首都圏で開始予定で、2027年度にはサービス提供地域の拡大を目指しています。
主要な自動運転タクシー・モビリティテストの比較
| 主導企業/パートナーシップ | 主要技術提供者 | 目標自動運転レベル | 車両プラットフォーム | 主要テストエリア(東京) | 報告されている状況/一般アクセス(2025年初頭時点) |
|---|---|---|---|---|---|
| Waymo / GO / 日本交通 | Waymo | レベル4(将来的) | Jaguar I-PACE | 都心7区(港、新宿、渋谷、千代田、中央、品川、江東) | 2025年開始:データ収集目的の手動運転。初期段階では一般アクセスなし。 |
| ティアフォー / (データ収集で日本交通) | ティアフォー (Autoware) | レベル4 | JPN TAXI(データ収集用)、Minibus 2.0、ロボタクシー試作車 | お台場、西新宿、他(広域展開計画中) | レベル2実証完了。レベル4商業化を2024年~2027年にかけて段階的に計画。限定的な試乗会/デモ実施。 |
| MONET Technologies / May Mobility | May Mobility | レベル4(2029年度目標) | Toyota Sienna | 臨海副都心(有明、台場、青海) | レベル2一般向け無料試乗(2025年1月~3月、現在は終了)。 |
| 本田技研工業 / GM Cruise | Cruise | レベル4 | Cruise Origin | 東京都心部(計画中) | 計画段階(2026年初頭目標との情報あり)。 |
| 日産自動車 | 日産自動車 | レベル4(将来的) | (特定情報なし) | 首都圏(計画中) | 2025年後半に実証サービス開始予定、2027年度に地域拡大目標。 |
運用フレームワークと規制環境
安全プロトコルと対策
現在の実証実験では安全性が最優先事項として扱われています。Waymoの初期フェーズにおける手動運転や、MONET/May Mobilityおよびティアフォーのレベル2実証実験におけるセーフティドライバーの同乗は、その証左です。
技術的な安全対策としては、複数の異なる種類のセンサー(カメラ、LiDAR、レーダーなど)を組み合わせることで、単一センサーの故障や弱点を補完し、環境認識の冗長性と信頼性を高めるアプローチが採用されています。
規制環境と政府の役割
2023年4月に施行された改正道路交通法により、特定条件下での完全自動運転(レベル4)が法的に可能になりました。国土交通省と経済産業省は自動運転技術の研究開発や実証実験に対して、補助金や資金援助を提供しています。
また、政府は大規模な実証実験を企画・主導しており、高速道路におけるトラック隊列走行や、路車協調システムの検証などが含まれます。東京都や川崎市といった地方自治体も、それぞれの地域での自動運転サービスの導入に向けて積極的に関与しています。
将来展望と社会的影響
商業サービスへの道筋
各プロジェクトの商業サービス開始目標時期は異なります:
- Waymo: 東京での商業サービス開始時期は「未定」
- ティアフォー: 2024年後半から2025年にかけて限定的なエリアでのサービス開始、2027年までに都内全域への展開を目標
- MONET / May Mobility: レベル4運行の目標時期を2029年度
- 本田技研工業 / GM Cruise: 2026年初頭を目標
- 日産自動車: 2025年後半に実証サービスを開始し、2027年度のサービス地域拡大を目指す
潜在的な社会的貢献
自動運転タクシーの普及により期待される社会的貢献には以下が含まれます:
- 労働力不足の緩和: 深刻化しているタクシーやバスのドライバー不足という社会課題への対応
- 移動の利便性向上: 高齢者や交通弱者を含む全ての人々にとって、より利用しやすく効率的な移動手段の提供
- 交通効率の改善: 交通流の最適化や事故の削減に貢献
課題と展望
東京の自動運転市場には以下の課題があります:
- 競争の激化: グローバルリーダーと国内勢の間での競争激化
- 複雑な都市環境への対応: 東京の複雑で予測困難な交通環境での安全かつ効率的な運用
- サイバーセキュリティ: ハッキングや不正アクセスに対するセキュリティ確保
- コストとビジネスモデル: 高額な開発・導入コストと競争力のあるビジネスモデルの確立
- インフラとの統合: 信号機情報連携や高精度3Dマップの整備・更新
- 社会受容性と倫理: 技術への市民の信頼醸成と事故発生時の責任問題
結論
東京は自動運転タクシー技術の開発と実証における世界的なホットスポットとして急速に台頭しています。Waymoの参入、ティアフォーの野心的な計画、そして他の多様なプレイヤーによる取り組みが相まって、活発な開発競争が繰り広げられています。
現段階では安全性の確保が最優先され、ほとんどの公道テストでセーフティドライバーの同乗や手動運転によるデータ収集が行われています。日本の自動運転開発は、政府による強力な後押しを受けつつ、ドライバー不足や高齢化社会における移動手段確保といった社会的課題への対応を目指しています。
自動運転タクシーの実用化への道のりは依然として挑戦的ですが、その実現に向けた動きは着実に加速しています。各社の競争と協調、そして官民連携の深化が、東京の未来の都市モビリティを形作っていく上で決定的な役割を果たすことになるでしょう。
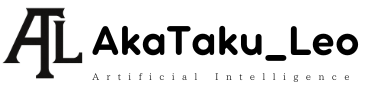



コメント