「新卒」の定義と対象層
今回話題となっている「新卒の失業率」とは、大学卒業後、間もない若年層(おおむね22~27歳)の労働者を指しています。 具体的には学士号以上(大学卒以上)を取得した新卒者が対象で、高校卒業者ではありません。 アメリカでは通常、大学卒業後数年以内の若者を「recent college graduates(最近の大学卒業者)」として統計上分類することが多く、この層の失業率が議論の焦点となっています。
失業率の推移(2022年~2025年)
| 時期 | 新卒失業率 | 備考 |
|---|---|---|
| 2022年後半 | 約4~4.5% | パンデミック後の景気回復に伴い底打ち |
| 2024年 | 5%台 | 景気減速と企業の採用縮小により上昇 |
| 2025年初め | 約5.8~6% | 近年まれに見る厳しい雇用情勢 |
| 2024年3月 | 約4.6% | |
| 2025年3月 | 約5.8% | 前年比で大幅悪化 |
この5~6%前後という新卒者失業率は、過去数十年で見ても異例の高さです。実際、「新卒失業率が全体の失業率を上回るのは少なくとも過去45年で初めて」と指摘する専門家もいます。 通常、大学卒の方が失業率は低い傾向がありますが、現在は新卒の若年層が全体平均より高い失業率となる逆転現象が起きています。
「30%上昇」の意味
報じられている「30%上昇」とは、失業率そのものが30ポイント増えたという意味ではなく、過去との比較における相対的な増加率(割合)を指しています。 例えば新卒者失業率が約4.5%から約5.8%に上昇した場合、これは絶対値では約1.3ポイントの上昇ですが、割合にすると約30%の増加に相当します。
実際、LinkedInのデータによれば「2022年9月以降、新卒大学卒の失業率は30%上昇した(対して全労働者平均の失業率は18%の上昇)」と報じられており、これが今回の「30%上昇」の根拠になっています。
業界別・地域別の傾向
業界別の影響
業界別では、テクノロジー(ハイテク)業界の影響が特に大きいと報じられています。オックスフォード・エコノミクスのレポートによれば、「最近の大卒者の失業率上昇は、需要が減退した分野に新卒者が過剰に供給されているミスマッチに起因する」とされています。
とりわけ技術業界(テック産業)がそれに該当し、近年コンピュータサイエンス等の専攻で卒業する学生が最多である一方、そのテック業界の求人が冷え込んでいることが指摘されています。 実際、IT企業各社は2022~2023年に大規模なレイオフ(解雇)を行い、新規採用を凍結または削減しました。この結果、ソフトウェアやデータサイエンスといった専門分野の新卒者に求人が行き渡らず、該当分野の失業率が上昇しています。
他の業界でもAI(人工知能)による自動化の影響で、エントリーレベル(初級職)の求人が減少しているとの指摘があります。LinkedInの経済担当役員Aneesh Raman氏は「テクノロジー、法律、流通(小売)など様々な業界で、従来新人が担っていた業務がAIに置き換わりつつある」と述べています。
地域別の傾向
地域別の顕著な違いについては、主要メディアではあまり言及されていません。 一般的にはテック企業の集まる西海岸や大都市圏で新卒採用縮小の影響が出やすいと考えられますが、統計上は全米的に大卒新卒者の失業率が平均して上昇していると報じられています。
背景にある経済要因
新卒者の失業率上昇の背景には、複数の経済要因が複合的に作用しています。
主な要因
- 景気循環と金融政策の影響: 2022年以降、米連邦準備制度理事会(FRB)は記録的なインフレを抑制するために急速な利上げを実施しました。この金融引き締め策により景気拡大ペースが鈍化し、企業の採用意欲も減退しました。実際、全米の求人件数は2022年3月に1200万件以上あったものが、2024年秋には740万件程度まで減少し、雇用の「売り手市場」だった状況が是正されつつあります。
- テック業界の急減速: パンデミック後にテック企業は一時的な人材需要の爆発で大量採用を行いましたが、その反動で2022~2023年にかけて人員削減と採用抑制に転じました。 例として、GoogleやMeta(旧Facebook)、Microsoftといった大手は新卒採用を大幅に減らし、VCのSignalFireによる調査では「大手テック企業での新卒採用数は2023年から2024年にかけて25%減少し、2019年(コロナ前)と比べても半分以下になった」と報告されています。
- AI(人工知能)の進展: 生成AIなどの台頭により、企業は定型的な初級業務を自動化できるようになりました。その結果、「新人に任せて経験を積ませる」タイプの職務が減少しています。 NY連銀の報告でも「企業はAIを活用して、本来なら新卒者が就くはずだった業務を代替している可能性がある」と指摘されています。
- 景気減速と不確実性: 世界的なインフレ高進や金利上昇、地政学リスクなどにより、企業は将来の景気に慎重な見方をしています。経済の先行き不透明感が強まると真っ先に採用計画の見直しが行われるため、新卒の求人も削減されがちです。
政府や企業の対応
政府・政策サイド
バイデン政権や政府当局から直接的な新卒雇用対策は今のところ大きく報じられていませんが、労働市場の動向自体は注視されています。FRBは金融政策運営の中で労働市場の冷却をある程度織り込んでおり、「雇用は強いが徐々に冷えてきている」と認識しています。 一方、連邦政府自体は若年層の雇用確保に向けた動きも見せています。例えばホワイトハウスは2025会計年度の連邦政府職員の若手採用を強化すべく予算投資を検討しており、「人材不足が懸念される政府部門で積極的に新人を採用する」姿勢を示しています。
企業・雇用者サイド
多くの企業は採用抑制や選考基準の見直しで対応しています。NACEの調査では多数の企業が新卒採用計画を縮小しており、現状では全体として新卒採用マーケットは買い手市場に転じている状況です。 その一方で、企業内での役割再編も始まっています。AI導入でエントリーレベル業務が減った分、一部の企業では新卒社員により高度な仕事を任せるケースも出ています。たとえば大手会計事務所のKPMGでは、新卒者に以前は経験者が行っていた税務業務を任せるようにするなど、新人に付加価値の高い経験を積ませる方向へのシフトが模索されています。
データの信頼性
この話題に関するデータや分析は、Bloomberg(ブルームバーグ)やWall Street Journal、CNBC、ニューヨーク連銀、オックスフォード・エコノミクスなど信頼性の高い情報源によって提供されています。たとえばブルームバーグはNY連銀の統計に基づき、新卒失業率が歴史的高水準にあることや新卒者の40%以上が不完全雇用状態であることを報じ、CBSニュースやCNBCはオックスフォード・エコノミクスのレポートやNACEの調査結果に言及しつつ状況を詳述しています。 またニューヨーク・タイムズ紙への寄稿やThe Atlantic誌のコラムでは、AIの普及と新卒雇用の関係に関する深掘りがなされ、今回の現象をより長期的・構造的視点から捉えています。
いずれのソースも最新の統計値(2025年前半時点)に基づいており、データの整合性も高いと言えます。
まとめ
米国の新卒失業率上昇は、景気減速、テック業界の採用縮小、AIによる初級職の代替、そして経済の先行き不透明感という複合的要因によるものです。特に注目すべきは、従来よりも失業率が低かった大卒層が全体平均を上回るという逆転現象が起きていることで、これは過去45年で初めての事態とされています。
この状況は一時的な景気循環以上の構造的な変化を示唆しており、AIの進展により企業のエントリーレベルポジションが変質している可能性があります。政府や企業も対応を模索していますが、短期的には新卒者自身がスキルアップや専門分野の見直しを迫られる厳しい状況が続くでしょう。
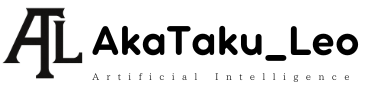


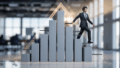
コメント